
樒は「しきみ」と読み本来仏式の葬儀に、お亡くなりになった方にお供えする供花となります。
樒はモクレン科の常緑木で、葉は固く、厚く光沢があります。1年を通して枯れることがなく、春には黄色の花を咲かせます。仏教ではとても大事な植物となります
樒が仏教にとって大事な木とされる理由
- 樒はインドから中国に渡り、日本へ入ってきたものです。奈良時代に律宗を開いた僧侶が唐から持ち帰ったもので、立派な僧侶が持ち帰ってもたらした木ということでその後仏教の中で使用されることになったと言われています。(諸説)
- 樒は仏様のいる世界に咲いている蓮華と似ていることから、仏教の中でも密教の儀式では使用されるようになりました。蓮華より手に入れやすいこともその理由の一つかとも思われます。
- 樒は傷をつけると強い香りを放ちます。この香りが虫を寄せ付けずまたご遺体の臭いを消してくれるため、通夜や葬儀の場に飾るのがふさわしいとされます。
- 樒は葉だけではなく、木、花、実とすべてに毒性があり、食すると中毒症状に陥ります。樒の強い毒性は獣除けとしても有用性があり、また邪なものを寄せ付けないということから清めの意味でも葬儀に使用されるようになりました。
- 樒は枝を切っても、水枯れをしなければ長持ちします。生花と違って枯れる細心の注意を払わなければならないことはないので非常に使用しやすい存在です。
仏式の葬儀で樒を使用するときとは
宗派や地域によって違いはありますが、以下の時に使用するものとされています
- 人が亡くなりますと、よく死に水を取ると言いますが、本来はお釈迦様が弟子に最後に水を飲ませてほしいというところからの言い伝えですが、近年ではお亡くなりになった後に故人様の口に水を含ませて差し上げるというように変わってきました。方法は、割りばしに脱脂綿を濡らして口元をぬらしたり、筆を水でぬらして、口元をぬらしたりとしていますが、樒の葉に水を乗せ、故人様の口元に垂らすことで使用しているところもあります。
- 亡くなった方を布団にご安置してお線香があげられるように枕もとの近くを整えます。今は沢山の花を枕花として飾ることや一輪挿しで菊の花を1本飾るとしているところもありますが、以前は亡くなった方の臭い、毒性のあるものから亡くなった方、周りの方を守るという意味で、花瓶に樒を飾っていました。宗派によっては儀式中に必要な仏具の一つとして今日でも使用されています。
樒と榊の違い
葬儀で使用される樒によく似た植物で榊というものがあります。榊は神道の儀式で使用するもので神道では樒は使用することはなく、またその反対で仏式で榊を使用することはありません。
榊(さかき)…榊も2種類あり本榊は葉に厚みがあり葉のギザギザがありません。葉が小ぶりでギザギザのあるものと2種類あります。どちらも左右対称に葉がついていて平面的で無臭です。
樒(しきみ)…葉が密集して枝ぶりが立体的で、強い臭いがあります。
近年は仏壇にお供えしている家庭も少なくなった樒ですが、本来の意味を理解して生花として樒をお供えしてもよいのかとは思います。

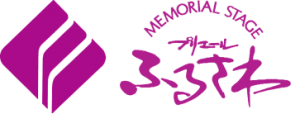

 0120-16-0199
0120-16-0199
どんなことでもお気軽に
ご相談ください!!